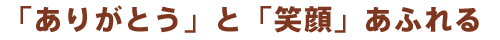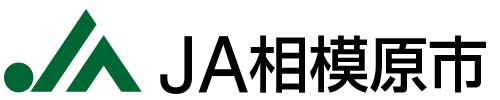トピックス
【広報取材】循環型水耕栽培を導入

相原支店の組合員、吉川寛徳さんは今年3月末にJAを退職後、資源循環型水耕栽培の取り組みを始めました。市内でも導入者が数えるほどしかいない生産システムを取り入れ、安定した生産方法の確立と長期的な規模拡大、新たな仲間づくりを目指します。
吉川さんは大学卒業後、JAへ入職。渉外担当などの支店勤務などを経て、営農担当部署の最前線である営農センターで、営農指導員として長年活躍してきました。職員時代から㈱アクポニが展開する、生産性と環境配慮の両立が期待できる生産システム「アクアポニックス」に注目し、いつか自身でも導入したいと考えていました。
このシステムは、最初に水槽で養殖する魚の排泄物を水中のバクテリアが植物の栄養素に分解。そして、その栄養素を植物が吸収して水の浄化装置の役目を果たし、きれいになった水が再び水槽に戻る仕組みです。水を一切捨てずに入れ替えることもなく、農薬・化学肥料を必要としないのが特徴。また、土耕栽培と比べて約半分の日数で収穫可能なサイズまで栽培が可能で、通年で安定した生産を見込むことができます。
都市化が進んでいるJA管内では、相模川沿いの地域を除き住宅街に畑が点在しています。このため、土ぼこりや農薬散布など、生産者の周辺住民に対する配慮がより一層必要な状況です。また、畑では連作障害の可能性がありますが、水耕栽培であれば回避も期待できます。
吉川さんは自宅敷地内に72㎡のビニールハウスを建設。ハウス内に500Lの水槽を2基設置し、そこにアフリカ大陸などが原産の「ティラピア」100匹を飼育しています。水槽では水温管理に細心の注意を払い、今年の夏はかつてない暑さに悩まされて40℃超を記録した一方、これからの時期は15℃を下回らないようにヒーターの稼働を徹底していきます。
現在、リーフレタスやロメインレタス、ハーブ類を試験栽培していますが、葉物野菜は葉が横へ広がっていくため、満足できる品質を実現するには、1700ある栽培穴すべてを活用できないことがこれまでに判明しています。
10月上旬にはJA役職員、同支店運営委員ら約10人が視察し、吉川さんから生産システムや現状の課題などを説明を受けました。同月17日には同支店の直売へリーフレタスを初出荷しました。購入した消費者は「量販店の商品よりも柔らかくて、苦みが少ない。野菜嫌いの子どもでも、食べやすいと思います」などと好評です。
吉川さんは今後、コマツナやチンゲンサイなどの生産拡大を目指します。また、同システムを導入している生産者が地域で数えるほどのため、他地域の導入農家と情報交換して栽培事例を共有し、今後の運営に活用していく予定です。
吉川さんは「農家を志す若い人にとって新たな就農形態の選択肢の一つとして紹介していきたい」と意気込んでいます。