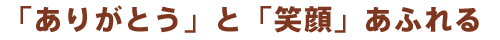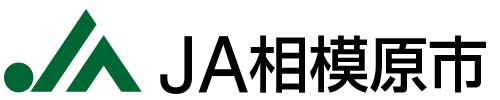トピックス
【広報取材】地域の水田を守る

新磯地区の西山和秀さんと髙橋一巳さんは、同地区を代表する水稲農家として米作りを通じて耕作放棄地化を防ぐなど、地域の水田を守り続けています。
同地区は市の南端に位置し、古くから相模川の豊かな恵みを享受してきた市内最大の米どころです。2人は自身が所有する水田以外に、それぞれ地域住民5軒ほどから耕作できなくなった水田を預かり米を栽培。西山さんが5ha、髙橋さんが10haを耕作する。品種は県の奨励品種「はるみ」や「キヌヒカリ」、「てんこもり」、「喜寿糯(きじゅもち)」を育てています。
西山さんは相模川河川敷のほとりに家を構え、酪農を営む家柄でした。平成20年、酪農に幕を下ろしてからは水稲栽培を本格化させました。近年の高温障害やカメムシの大量発生に加え、全国的に分布が拡大しつづける特定外来生物の「ナガエツルノゲイトウ」が同地区でも発生し始め、駆除に腐心しています。普段の作業は一人で行うことが多いため、繁忙期には特定非営利活動法人「援農さがみはら」の援農ボランティアによる収穫作業の応援を頼みますが、それでも3週間かかりきりだといいます。
髙橋さんは農業を父から引き継いで19歳から半世紀にわたって同地区の水田を守り続けてきました。10人ほどの地域の仲間と一緒に米作りに取り組みます。機械いじりや修理が得意な髙橋さんは、自作で機械や構造物を設置してしまうほどの技術を持ち、地元の同級生でもある西山さんから農機のメンテナンスを頼まれる関係です。
米作りには数年前から地元出身の池田彰太さんも加わるようになりました。幼少期から祖父の米作りを手伝うようになり、今年は一般企業で仕事をこなしながら60aを耕作しています。米作りの2人の大先輩は、次代を担うホープに対して惜しみない技術の伝承を進めています。
西山さんは「貴重な農地を守るとともに、水田1枚あたりの面積を拡大し、作業効率化を目指したい」と意気込んでいます。一方、髙橋さんは「事故や熱中症など、安全に収穫まで辿りつくことを一番にしたい」と語ります。