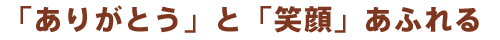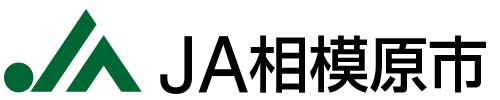トピックス
【広報取材】伝統の当麻梨 今年も最盛

JA管内でわずかに生産されるブランド梨「当麻梨」が最盛期を迎えています。都市化が進行する中で生産者は現在2軒まで減少する一方、現在でも全国から根強い人気を集めています。栽培環境が変わりゆく中、周囲に配慮しながら伝統の味を守り続けています。
戦後の1953年、行政が南区の当麻耕地を土壌検定した結果、「ナシ栽培に最適」と評されました。これを受けて当麻地区の農家9人が「当麻果実組合」を結成し、ナシ栽培が始まりました。相模川河川敷に位置する同地は、地下8mほどから汲み上げる豊富な井戸水に恵まれています。また、水はけの良い土壌がナシ栽培に適しているといいます。
その後、生産者が増え続け、1960年代には当時のメイン通りだった国道129号線(現県道508号線)で沿道直売を試行し、その後25軒の農家が本格実施。同組合の人数は最大34人まで増え続けた歴史を持ちます。
同地区で「春山梨園」を営む春山秀男さんは、当麻梨を守り続ける生産者の一人です。ナシを約150本と水稲を約40a営んでいます。春山さん宅では60年以上前から栽培を続けてきましたが、自身は仕事を定年退職してから本格参入しました。
春山さんは、日当たりを考慮した枝の剪定作業や授粉に加え、防除作業を重要視しています。樹木1本に対し10日に1回、1本ずつ丁寧に農薬を散布。木の状態を観察して防除歴を残しています。圃場の周りはかつて田畑が広がっていましたが、現在は高速道路のインターチェンジの設置や大型ホームセンターの出店などの開発が進み、工場や住宅が隣り合うようになりました。そのため、農薬が周りに広がらないように配慮した防除作業が必須となりました。
収穫時期は稲刈りの時期とも重なるため、最盛期には兄弟を含めた家族総出で作業にあたっています。当麻梨は赤みをほのかに帯びて完熟するまで熟成するのが鉄則。その分、取り扱いがデリケートとなるため、購入後は早めの消費を呼びかけています。常連客からは「当麻梨はみずみずしくて糖度が高く、一度口にすると他の梨は食べられない」と評判です。
昨年の収量は約1.3㌧で、今年も同程度の収穫を見込んでいます。自宅での直売をメインに、北海道から沖縄まで毎年200軒弱の固定客へ発送。加えて、市内養鶏農家の直売所とJA農産物直売所「ベジたべーな」へ出荷し、養鶏農家への出荷は卵販売の呼び水にもなっています。8月上旬の「新水」からスタートし、11月上旬まで「幸水」「豊水」など8種類を出荷予定です。
春山さんは「地元で長年続く名産として、手塩をかけて育てた梨の甘みには自信があります。消費者には、完熟のおいしさをぜひ知ってほしい」と呼び掛けています。